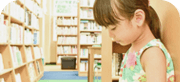図書館システムの共同利用
おすすめの図書館システムを種類別にチェック
公開日:
|更新日:
本記事では、図書館システムの共同利用について詳しく解説します。
図書館システムの共同利用とは?
共同利用の目的
図書館システムの共同利用とは、複数の図書館がひとつのシステムを共有する方法です。
複数のシステムを統合することで、リソースの一元管理が可能となり、蔵書数の拡充や運用コストの削減につながります。
膨大な蔵書をひとつのシステムで運用管理できるため、貸出状況を一元的に管理できます。ユーザーの利用状況の把握や、サイバーセキュリティ対策を目的とする場合もあります。
共同利用の方法
図書館システムを共同で利用するためには、複数の図書館でシステムを共有するための合意が必要です。
次に、アクセスや管理の柔軟性を確保するためにクラウドベースのシステムを選び、API連携によってシステムを統合して、蔵書検索や貸出予約ができるようにします。
ユーザーがいずれの図書館からでも蔵書を検索・予約できるよう、各図書館の蔵書情報を統合したデータベースを作成します。作成したデータベースを図書館で共有するとユーザーによる横断検索が行われ、システムの共同利用が開始する流れです。
共同利用のメリット
共同利用する施設の蔵書を一括で検索できるようになり、図書館間の相互利用を促します。システム上では仮想的なひとつの図書館として運用されるため、ユーザーは豊富な蔵書の中から選べるようになります。
蔵書を一元管理することで、ユーザーの選択肢が広がり、貸出手続きも円滑に進められます。また、蔵書のある図書館まで移動する手間が省けます。さらに図書館の利用促進に加え、システムを共有する大学や公共図書館の連携が強まり、地域の活性化にもつながります。
共同利用のデメリット
図書館システムの共同利用では、図書館ごとの意思決定や運用方針が異なる場合に、連絡や調整が必要になることがあります。
ユーザー情報や蔵書データを統合する際には、プライバシー保護や情報管理の課題が発生するおそれがあります。また、システム障害が発生した場合には、広範囲に影響が及ぶ可能性もあるため、事前の対策が求められます。
図書館システムの共同利用の事例
複数の大学での共同利用事例
私立総合大学である早稲田大学と慶應義塾大学が、保有する図書館(メディアセンター)の図書館システムを共同運用した事例です。
1986年より図書館間協定を締結していたことから、すでに図書館の相互利用を実施していましたが、システムを共有したことで書誌データの共同調達・共同運用やシステム運用コストの低減につながりました。
共同利用以外にも図書館システムの基礎知識をチェックしよう
図書館システムは、蔵書の管理や貸出業務などの業務全体を効率化します。共同利用はひとつのシステムを複数の図書館で運用する方法で、すでに大学でも導入されています。
当サイトでは、図書館システムの費用相場やシステムを導入する流れについて紹介しています。次のページもぜひ参考にしてください。
図書館システム・会社一覧と
選び方のポイント
種類別に探す図書館システム
図書館の種類によって利用者の求めるサービスや情報の範囲が異なります。例えば、公共図書館では貸出・返却処理の効率化が重要であり、大学図書館では学術的な検索機能やリポジトリ管理が求められます。
適切な図書館システムを選ぶことは、図書館の運営効率化だけでなく、利用者の満足度向上や継続利用につながります。
当サイトでは、図書館の種別ごとに人気システムを調査し、掲載していますので、導入の参考にしてください。